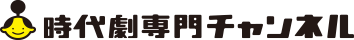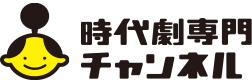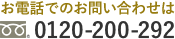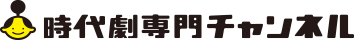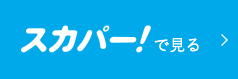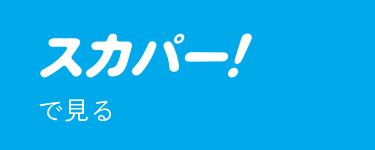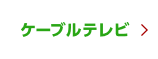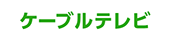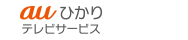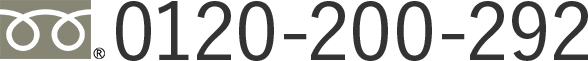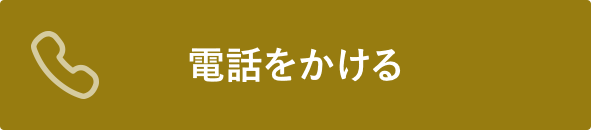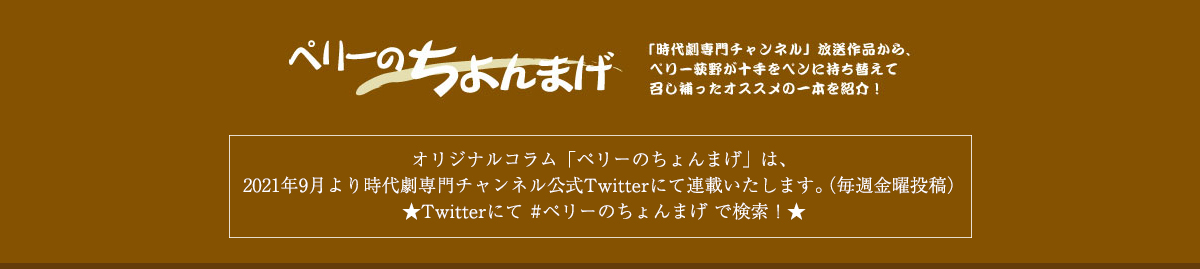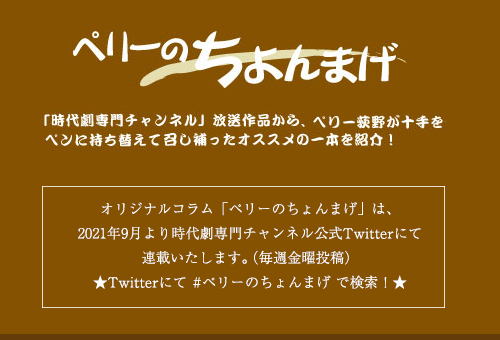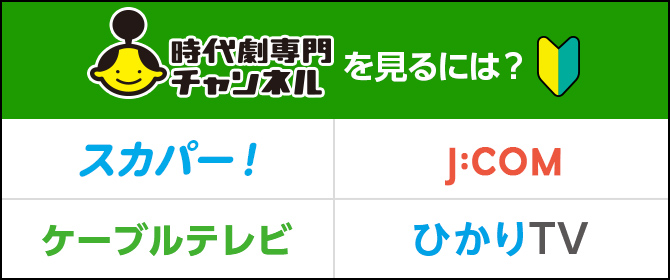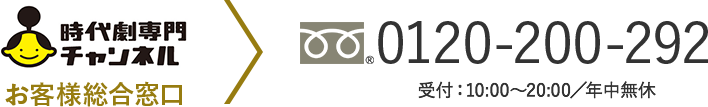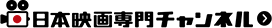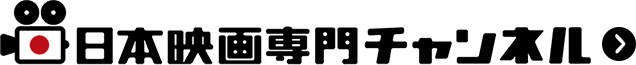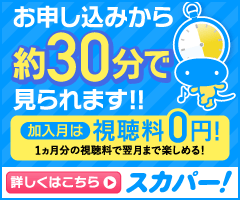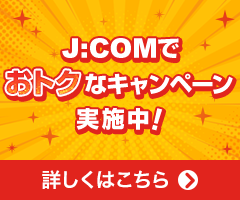1962年愛知県生まれ。大学在学中よりラジオのパーソナリティ兼原稿書きを始める。 「週刊ポスト」「月刊サーカス」「中日新聞」「時事通信」などでテレビコラム、「ナンクロ」「時代劇マガジン」では時代劇コラムを連載中。さらに史上初の時代劇主題歌CD「ちょんまげ天国」シリーズ全三作(ソニーミュージックダイレクト)をプロデュース。時代劇ブームの仕掛け人となる。
映像のほか、舞台の時代劇も毎月チェック。時代劇を愛する女子で結成した「チョンマゲ愛好女子部」の活動を展開しつつ、劇評・書評もてがける。中身は"ペリーテイスト"を効かせた、笑える内容。ほかに、著書「チョンマゲ天国」(ベネッセ)、「コモチのキモチ」(ベネッセ)、「みんなのテレビ時代劇」(共著・アスペクト)。「ペリーが来りてほら貝を吹く」(朝日ソノラマ)。ちょんまげ八百八町」(玄光社MOOK)「ナゴヤ帝国の逆襲」(洋泉社)「チョンマゲ江戸むらさ記」(辰己出版)当チャンネルのインタビュアーとしても活躍中。